


瓦版2024.07.09 第714号 斉藤 睦さんら11人のコラム掲載。

瓦版2024.06.25 第713号 川島英樹さんら10人のコラム掲載。

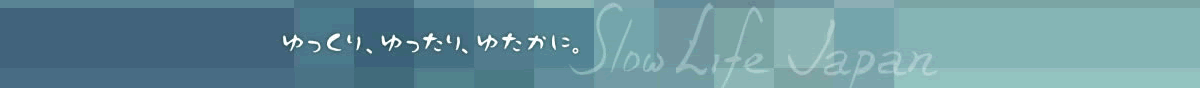
週刊スローライフ瓦版 (2010.11.30 第32号)発行:NPOスローライフ・ジャパンスローライフ学会=======★★★★★11月12~14日富山県砺波市・南砺市で開催された“スローライフ・フォーラムinとなみ野。先ずは分科会報告です。http://www.slowlife-japan.jp/modules/katudou/details.php?blog_id=103★★★★★ このメールは毎週火曜日の発行です。NPOスローライフ ジャパンとのご縁を頼りにお送りしています。初めて受信 される方も含めて、お気軽にお付き合いください。コラム<火曜日の鐘> 斉藤睦(地域総合研究所所長)~~~ 150年住宅 2週間前に開かれた富山県となみ野フォーラムは、いろいろな意味で刺激的なフォーラムでした。とくに、「住まい」のスローさに驚嘆。 京の“着だおれ、大阪の“喰いだおれは良く聞くけれど、富山は“住みだおれというそうですね。つまり、住まいにお金をかけるということで、お話をうかがった典型的な散居村(大きな屋敷とそれを囲う屋敷林の村)タイプのお家では、部屋の数は13か14か正確にはわからず、4代前が骨格をつくり、3代前が天井を葺き、2代前が壁や欄間を工作し、自分がキッチンをリニューアルし、息子には外回りをせよと言い伝えているそうです。各代の支出は住居一軒分をつくるくらいの費用らしく、それを一軒のお屋敷に費やし、これまで百数十年もたせてきて、これからも受け継いで行く世代がいる地域があるとは。日本の中のヨーロッパ中世のたたずまいと言ってもいいかもしれない。 でも、その散居村にも跡継ぎのいない家も出てきはじめているという…。 年季の入ったスローな住宅をどう受け継ぐシステムをつくったらいいのだろう。1地域だけのテーマというよりも、日本中で考えなくてはいけないのではないだろうか。■街角から畦道から ————————————————–自然薯栽培発祥の地 吉田康知(山口県柳井市・やまぐちフラワーランド次長) いまや全国へ普及した自然薯の人工栽培―。その発祥の地が、山口県柳井市 であることを知る人は存外に少ない。政田自然農園の創業者、政田敏雄さん (平成17年没)は、今から40年以上も前に自然薯人工栽培への挑戦を決意し、 良質の自然薯の産地として知られる九州の山々を歩き回った。 時代が平成へと移り、調査した山の数が200を超えた頃、表が白で裏が黒の 2色のビニールシートや栽培用塩ビ製パイプを相次いで開発、山と同じ土質 環境・温度・湿度を作り出し、人工栽培に成功し、それが全国へと波及した。 発祥の地としても負けていられない。地元の農事組合法人「やまぐち自然薯 生産組合」は4年前から自然薯オーナーを募集している。年間5000円で、 うまく育てば6本の自然薯がわがものとなる。 今月21日に開かれた収穫祭には、県内外から170人のオーナーが集まり、自 然薯で作った団子の入った鍋に舌鼓を打ったばかりだ。———————————————————————-学会コラム<緑と絆の木陰> ~~~~~ 坪井ゆづる(朝日新聞編集委員・論説委員) 「名古屋」の民意の行方 名古屋市議会のリコール問題が、ぐじゃぐじゃになってきた。反議会の世論の爆発は、どこへ向かうのか。 実は私は、5年半前から今回のような世論の爆発を待っていた。きっかけは05年4月28日付の朝日新聞「私の視点」の「議員への手当が過剰だ」という投稿記事だ。名古屋市議会の則竹勅仁議員が書いた。 議会や委員会に出ると1日に1万円の費用弁償が支給される。月額101万円の議員報酬とは別枠だ。市議は地下鉄や市バスの無料パスも持っているだけに、どう考えてもムダであり、自分は返上しているという内容だった。 この「私の視点」は、則竹さんの「返上」を聞いた私が執筆をお願いした経緯があった。当時、すでに先進自治体では議員特権への批判が広がっていた。名古屋市の実態が載れば、市民の怒りを買い、議会も手当をやめざるを得ないだろうと思っていた。だが、議会はまったく態度を改めなかった。その厚顔さ、鈍感さに驚くとともに、怒ろうとしない住民にもがっかりした。 そんな住民がやっと怒った。その怒りはリコールが不成立でも、来春の統一地方選で明確な民意となって現れることになる。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━PR━━「KDDI」から・・・あなたが隠した宝物を、世界の誰かが探す。小さくてもあたたかなつながりを実感できる時間。この↓「ちいさなタカラ」で遊んでみてください。http://www.kddi.com/smile/index.html━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━PR━━「たかおか屋」から・・・ 「スローライフ・フォーラムinとなみ野」ご参加のみなさま、富山県でのお米の味はいかがでしたか? 高岡から味に自慢の〝こしひかり〟のご紹介です。http://www.takaokaya.jp/news/2010/11/26-151248.php━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■まち・むらニュース ————————————————・新潟県上越市 「新幹線の駅名募集中!」 平成26年に北陸新幹線が開業するにあたり、上越市に建設される駅名を考え ようと有志が集まって「新幹線駅名を考える会」を発足。地元の声だけでは なく、全国各地にお住まいで上越・妙高にゆかりのある方々にもご意見を、 とネットアンケートを実施中です。関心のある方はぜひ1票を。 http://station-name.jp/research/———————————————————————-コラム<象さんの散歩> 東京・地下鉄マナー⑥~~~ 前々号に「携帯電話の優先席での禁止令が無視されたままでは“顧客政策“が問われる・・」と書いた。もっと恐いのが、地下鉄駅構内の長い長いエスカレーターでの駆け降り族の横行であろう。「駆け降りは危険です」という掲示もどこ吹く風。疾風が飛びぬける。あの、かたかたかたの「ミュール」の音こそ、やや減ったものの、靴の高響きは絶えない。氷の風が吹く心地である。 こんなファーストな危険行為を掲示と放送に任せっぱなし。もし事故が起きたときには「警告していたのに・・」と、免罪符に使うのだろうか。 このエスカレーターで、マナーが完全に励行されている不思議な現象がある。「右側通行」。愉快にも大阪では「左側通行」。だれかのお願いでも命令でもない。危険への防衛本能だろうか。疑問符つきマナーである。∧ 川島正英 ∧━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━PR━━「日光『食』の研究所」から・・・知り合いの人から、有害駆除で取った地元の鹿を頂きました。鹿刺しとかが美味しいのでしょうが、今回は何と、カツ丼にしてみました。http://nikkokekko.blog121.fc2.com/blog-entry-67.html━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━コラム やまさかのぼる <暦と季節と暮らしと> その29 ~~~ ホンモノ麦酒新銘柄でカンパイ! 来週官暦12月6日から「しもつき」。寒さがいやが上にも身に沁みる時節になります。やっぱり、いいお酒で心身を温めることを心がけたいものです。 今秋は、麦酒党の小生にとって嬉しい動向が見られています。大手会社は、毎年秋になると、新しい製品を市場に送り出します。それが、ややもすると、単に酒精度を上げて酔いやすくしただけだったりしていました。 それが、今年は、各社それぞれに原材料に麦芽(モルト)以外のデンプン(米など)は使わない新銘柄を打ち出しています。酒精度を1割方上げていたりはしますが、まずは原材料面でのホンモノ尊重の取り組みを歓迎しましょう。 というわけで、今回は、我々の人生と生活の質を高めるホンモノ麦酒の新銘柄でカンパイ! コラム 野口智子<スローライフ曼荼羅> 「あしかが逸品堂」オープン~~~栃木県足利市の「一店逸品運動」のお世話をして、もう4年になります。先日空き店舗を借りて、会員みんなで「逸品堂」をつくりました。逸品を売るだけでなく、店主が先生となり体験スクールをやる「学び」のスペースとメニューを用意したことが特色です。日本最古の「足利学校」を持つ地域での「学び」がテーマの逸品運動。この店のオープンでかかわる店主たちも学ぶこと大です。http://noguchi-tomoko.com/modules/yutoriaruki/details.php?blog_id=81■事務局からのお知らせ△先週は、スローライフ学会“となみ野フォーラム”の思い出メモの第一回を お届けした。全体の流れと感謝のことばだった。きょうは、三つの分科会に ついて。わがホーム・ページにも掲載しているコーディネーター報告を引用 させていただきながらの印象記とでもいえるでしょうか。<利賀分科会>「地域の魅力と活力が交流をつくりだす> コーディネーター 丸岡一直(社会福祉法人二ツ井ふくし会理事長) パネリスト{地元側}中谷信一(財・利賀ふるさと財団理事長) 畠山芳子(武蔵野市からの移住者) {外から}大和田順子(一般社団法人L・B・A共同代表) 渋谷和久(国交省総合政策局政策課長) 過疎地域での活動例で高い評価を得てきた利賀村。分科会も、ここに移住 して10年の畠山さんが「夢とロマンはむらの中にこそあった」と語ったし、 ロハスの考えを提唱する大和田さんは都会の若い女性たちの目が「農山村の 無口な男性」に向きはじめたことを紹介した。 こういう過疎地と過密都市との「二地域居住」。国交省政策課長の渋谷さ んの提唱であった。畠山さんの「Iターン」も多様な組み合わせ事例の一つ で、 あらためて日本の「住まう」の新しい課題として考えてみたい。 だが、利賀村の現実からも眼を背けてはなるまい。丸岡さんも、村の活動 を主導してきた中谷さんに「憂いの表情が見え隠れしていた」「人口減少が 止まらない事態はよそ者が感じるよりはるかに深刻」と、こまやかに見る。 <井波分科会>「美しく楽しく過ごす技と祭りと味と」 コーディネーター 坪井ゆづる(朝日新聞論説委員・編集委員) パネリスト{地元側}岩倉雅美(井波彫刻協同組合理事長) 杉森桂子(NPO心泉いなみ理事) {外から}藤田穣(総務省自治行政局過疎対策室長) 田嶋義介(島根県立大名誉教授) 農業に生きて、暮らしに知恵と工夫を積み重ね、楽しく、文化ゆたかに 過ごしてきた「となみ野」。分科会でも、地元勢の元気さが際立った。 「居宅が大きすぎませんか」との問いに「空間が人間を育てる」「天井が 高いほど賢い子が育つ」と。農業を通じた交流の楽しさも報告された。 総務省の藤田さんは「都会では断絶しがちな世代間の絆」の深さを指摘、 田嶋さんは「家屋、車、家電、衣(ころも)」在来型4Kから「観光、環境、 健康、介護」の新需要4Kに移って「田舎の価値が上がっている」と。 もちろん現実の問題点も浮かぶ。坪井さんは「4世代が当たり前だった散 居村でも、少子高齢化がすすむ現状」を課題の一つとしてあげた。<砺波分科会>「散居村の景観と暮らしを守ろう」 コーディネーター 斉藤 睦(地域総合研究所長) パネリスト{地元側}尾田武雄(NPO砺波土蔵の会理事長) 砂田龍次(となみ散居村ミュージアム館長) {外から}長谷川八重(NPO法人スローライフ掛川理事) 早野 透(桜美林大学教授) 日本の農村に「住まう」すばらしい文化遺産である散居村。分科会で、斎 藤さんは、参加者に挙手で意見を聞き、それでも、ここに暮らし続けること へのためらいが多いと読みとって、論議を進めた。長谷川さんは「通年型の 暮らし再発見活動をしないと・・」、早野さんは「これだけの散居村の個性 的で貴重な姿を知らない人はたくさんいる。もっと情報発信したほうが良い」 と発言。 一方、散居村の暮らしと文化継承活動をしている尾田さんは「散居村で活 性化というが、心の教育が先。当たり前と思っている暮らしの再評価を住民 自身がすることが大事」。散居村ミュージアム館長の砂田さんは「散居村は 先人の知恵、努力の結晶。失ってから大事さがわかるのでは遅いので、価値 の再発見勉強会を年40回やっている」と語る。ここがポイントだろう。 小世帯化する家族が大きな家と屋敷林をどう管理するか、二地域居住や民 宿の活用などの課題を残しつつ議論の継続が大事、と斎藤さんはまとめた。 (川島正英)△筑紫哲也賞「作文コンクール/神話・民話を読み継ぐ」の入賞作品集をネット上(e-book)で公開中!◆「上巻」→ http://www.slowlife-japan.jp/web_vol1/flipviewerxpress.html◆「下巻」→ http://www.slowlife-japan.jp/web_vol2/flipviewerxpress.html△スローライフ学会へのお誘い スローライフ学会はNPOスローライフ・ジャパンが運営する学会(学長・神野直彦、会長・増田寛也)です。 楽しくスローライフについて多くの分野から学び語り合います。また、全国でスローライフなまちづくりをすすめる皆さんとのつながりでもあります。 年会費5000円。会員は自動的にNPOのサポート会員となります。会員になっていただけれんば、この「瓦版」に記事を出したり、「さんか・さろん」などで交流したりできます。「学会便り」や、各種ご案内もお届けします。 また、学会申し込みはこちらから↓http://www.slowlife-japan.jp/modules/liaise/index.php?form_id=5=======■いつも応援していただき、ありがとうございます。日本テレネット株式会社 http://www.nippon-tele.net/クオリティ株式会社 http://www.quality.co.jp/KDDI株式会社 http://www.kddi.com/株式会社ダイイチ http://www.co-daiichi.co.jp/boring.htmlアース・デザイン・インターナショナル(edi)株式会社 http://www.edi.ne.jp/=======最後までお読みくださって、ありがとうございました。このメールマガジン、あるいは当団体へのご意見、ご質問はこちらへまた、今後、このメールマガジンの送信が不要という場合、あるいはメールアドレスの変更をご希望される場合もこちらへご連絡ください。この「週刊スローライフ瓦版」、バックナンバーをアップしています。まだご覧になっていない方、こちらからご覧ください。http://www.slowlife-japan.jp/modules/mailmagazine/details.php?blog_id=2=======Copyright(C) NPO法人スローライフ・ジャパン スローライフ学会◆事務所を移転しました。↓↓↓↓↓ 新連絡先です ↓↓↓↓↓〒160-0002東京都新宿区坂町21 リカビル301TEL 03-5312-4141 FAX 03-5312-4554 http://www.slowlife-japan.jp/”