


瓦版2024.07.09 第714号 斉藤 睦さんら11人のコラム掲載。

瓦版2024.06.25 第713号 川島英樹さんら10人のコラム掲載。

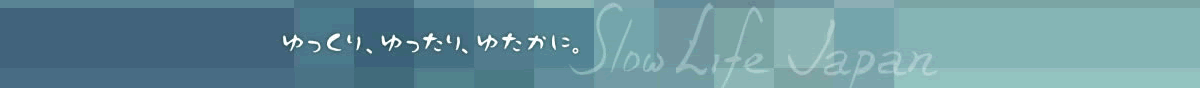
週刊スローライフ瓦版 (2012.3.20 第99号)発行:NPOスローライフ・ジャパンスローライフ学会=======★★★★★あす21日の「さんか・さろん」は、映画と講演の夕べ。いい雰囲気の会場で「幸せの経済学」を観たり、神野直彦・わが学会学長の特別スピーチを聴いたり。席にまだ余裕があります。詳細は「編集室たより」とHPでどうぞ。http://www.slowlife-japan.jp/modules/katudou/details.php?blog_id=139★★★★★コラム<火曜日の鐘> 山下茂(明治大学公共政策大学院教授)~~~ 「絆」「ネットワーク」そして「レースワーク」 大震災以来、「絆」や「ネットワーク」が大切にされている。字義で言うと、「絆」は一筋の綱、netは「網」、networkは「網状の物」で格子状だ。 ただ、人々や地域の繋がり方は、一直線だけの「絆」や「網」だけではない。よく見れば、一つの結び目にあちこちから沢山の糸が結ばれていたり、隣りの結び目を越えて遠くに繋がっている。ずっと複雑だ。そういう繋がり方は「カオス」状に見えても、個々の点同士の繋がりは沢山の「絆」である。 糸の複雑な繋がり方は模様を生む。人と人との関係の全体を一口に表わすには、糸の繋がりが模様になっている「レース」(lace)とか「レースワーク」(lacework)という喩えの方がよい。「絆」や「網目」も喩えなのだが、それが十分に実際の人々の繋がり方を表現し切れていないからだ。(つづく)学会コラム<緑と絆の木陰> ~~~~~ 中村桂子(JT生命誌研究舘館長) 植物っぽく生きる 先日新聞に可愛い白い花の写真があり、「3万年前の花」との見出しにびっくりしました。シベリアの永久凍土の中で見つかった実の中のタネをまいたら花をつけたとか。植物の生存戦略はすごいなと思います。ナデシコ科の白く可憐な花ゆえに余計それを感じました。 現代生物学はその基本を、生きものはすべて一つの祖先から生まれた仲間であり、皆同じというところに置いています。それはとても大事なことですが、最近は、でも違うところがあるよねという方に興味があります。違うということを、差別でなく差異として見ることの大切さも含めて。 そういう眼で見ると、動物と植物は同じ祖先から生まれたのにとても異なる生き方をしている・・・。日常の眼ではそんなのあたりまえと思われるでしょうが、科学の眼では基本は同じなので、そこを踏まえたうえでやはり違うなとなるのです。このような立場で改めて植物を見ると、やはり「長い時間の中で続いていく」という戦略に長けています。 私たちも長い時間を意識し、植物っぽく生きてもよいのではないかと思ったりしています。いわゆる草食系とはちょっと違う意味で。 ■街角から畦道からバトンを渡す 綿貫涼子(東京・新宿、民間企業広報スタッフ)ちょっとした空き時間にふと立ち寄ったお店。雑貨屋さんかな?と思ったら、洋服も置いてある。商品には、値札にしては大きな約10センチ四方のタグが。小さな顔写真と商品についてのコメントが書いてあった。店員さんが説明をしてくれた。「売り手が顔と名前を明かして出品するリサイクルショップです」タグには、出品者の名前、顔写真と商品に対する思い入れやストーリーが値段とともに書かれている。商品を預かり店舗に並べ、売れた時点で売上を出品者とお店が折半する仕組み。短時間なのに、ついいくつか購入してしまった。出品者は60代の女性。亡きお父様がジュエリーデザイナーで、1950年代にアメリカのジュエリーショーを一緒に周ってサンプル用に購入したアクセサリーを、かなり出品されていた。普通では手に入らない昔のアメリカのアクセサリー。思わぬ出会いにちょっとワクワクした。「よろしければ出品者にメッセージをお願いします。」とカードとペンを手渡された。「PASS THE BATON(バトンを渡す)」がお店の名前。バトンをもらう、ちょっと不思議な、でも温かい気持ちになったお買い物体験だった。PASS THE BATON http://www.pass-the-baton.com/瓦版100号におもう 中村友子(千葉市在住、ライター) 3・11の震災から1年が過ぎ、家族を亡くした人たちの悲しみは癒えることなく、その悲しみに背中を押され現実を生きている毎日だと感じます。 スローライフの生き方が、安心して生きる場所作りの基礎となり、手をつなぎ合い、小さな島国のどこでも、地方も、過疎の村もなく平等に暮らせる社会が来ることを願いたいです。そのためにも、瓦版のメッセージが、みんなの心の鐘を鳴らして、力をくれることを期待します。■まち・むらニュース ————————————————・鳥羽市 “食を切り口に「ぐるとば」開催中あなたの知らない鳥羽を味わう10日間、ということで、鳥羽市内でカキ、ワカメ、伊勢エビ、トコロテン、ナマス、など様々な“食に触れる体験観光を実施中。いずれも地域の人たちが自ら体験プログラムを企画した、珍しいものばかり。単なる旅館の料理とは違う、多様な“食の楽しみ方が提案されています。期間限定のため、いざ、鳥羽へ!3月25日までです。詳しいプログラムはこちら↓http://www.city.toba.mie.jp/kanko/gurutoba/top.html問い合わせ「新しい鳥羽の食旅創造委員会」鳥羽市観光課 ℡0599-25-1155・三重県 三重津海軍所跡で「世界遺産フェスタ」を開く佐賀市川副町、諸富町にまたがる「三重津海軍所跡」は、日本初の実用蒸気船凌風丸(りょうふうまる)を造った幕末佐賀藩の遺跡。世界遺産登録を目指す「九州・山口の近代化産業遺産群」の構成資産候補として、調査研究が進む。船の建造・修理を行うドックエリアの木製護岸が発見されるなど、さまざまな成果が得られ、3月18日(日)に世界遺産フェスタを開催する。楽しみながら幕末佐賀の歴史に触れてみよう!というイベント。出土品や遺構の写真パネル展示、幕末佐賀藩についての講演会やトークショーなども。また、屋形船で早津川周遊ができる。(11時、13時、15時の3回で先着45名)子ども向けには石炭で動くミニSLの乗車会、佐賀のゆるキャラたち遊びなど。http://www.pref.saga.lg.jp/web/kankou/kb-bunka/sekai-isan/_49322.html問い合わせ先佐賀県統括本部 政策監グループ 文化創造・世界遺産推進担当電話:0952-25-7186 メールアドレス: seisakukan-g@pref.saga.lg.jp━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━PR━━「日光『食』の研究所」から・・・高校生を対象に開催している「日光市まちづくりアカデミー」の活動の中で、作られたグルメマップ。美味しくてお手ごろ価格なお店が紹介されています。http://nikkokekko.blog121.fc2.com/blog-date-20120316.html━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━PR━━クオリティライフから・・・玄米菜食とは、野菜の旬とは、オーガニックとは、食の安全とは、などを一日で学んで資格を得られる「ナチュラルフードアドバイザー講座」を開催いたします。詳しくはこちらから→ http://tabegoto.jp/archives/105━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━コラム<象さんの散歩> 世田谷に「キッチンが走る」~~~ 俗悪なお笑いとおふざけにうんざりのテレビではあるが、もちろんいくつかいい番組もある。NHKの金曜日夕の番組「キッチンが走る」は、その一つ。杉浦太陽という青年俳優が、地方へ出かけてキッチン車を走らせる。その土地の食材を求め、つくり手と語り合う。週代わりで登場する料理の達人が、集まった材料だけで食事をつくる。食材のつくり手を招いてご馳走する。 先週は、この車が東京・世田谷を走った。料理人は、名門・吉兆で修業、和の創作料理で名を成した笠原将弘さん。この日、城南小松菜、長ネギ、菜の葉、産みたて卵が集まった。先祖代々の農作をまもって、有機肥料を探して、学校給食にも提供して・・といった話も聞く。「百姓だから、百の仕事ができるのですよ」。笠原シェフが、そんな心意気を料理にデザインしたい、と。 東京の、それも世田谷の、都市エリアの真ん中に「むら」が残されていた。知恵と労苦の積み重ねで歴史を生きぬいてきた文化が・・ ∧ 川島正英 ∧コラム やまさかのぼる <暦と季節と暮らしと>その94~~~ お月様ベースで世界暦を! さあ、「春分」だ!筆者がずゥーと主張していることだが、各地、各国共通で、「歳首」と位置付けしうる日だ!ここから、次第に日が長くなるゥ~。 もちろん、昔のケルトのように「冬至」を歳首とするのも素晴らしい。ただ、「春分」でも「冬至」でも南半球は納得できまい。暑い中でお祝いして来たイエスさんの誕生日とは意味が違う。イスラムの人たちだとどうなのだろうか? それで思うのだが、いっそ陰暦で世界共通暦を決めたらどうか?筆者は南半球に行ったことがないので、南でお天道様とお月様がどう動いているのか、アタマでも分かっている気がしないし、心ではまったく信じられていない。 でも、たぶん、お月様の出入りは違っても、満ち欠けは夏も冬も関係ないだろう。いつも南北共通のお姿ならば、世界暦の基礎にふさわしい・・・? コラム 野口智子<スローライフ曼荼羅> 回転寿司べえべえ~~~まちおこしで、特別の人が特別に何かをやるのは簡単なことですが、ごく普通の人たちの中で新しい動きが起きてその運動が市民権を得ていくことは大変だと思います。新潟県胎内市での米粉のまちおこし、ついにごく普通に、回転寿司でも米粉メニューが登場しました。米粉製のクレープ状のもので具を巻いて食べる新しい食べ方“べえべえ。「べえべえのマグロ~!」と声が飛びます。http://noguchi-tomoko.com/modules/yutoriaruki/details.php?blog_id=149 ■編集室だより「瓦版100号」へのメッセージをよろしく・・このスローライフ瓦版が、来週、次の号で「100」を刻みます。編集室からの「100号におもう」をよろしく、とのお願いに、中村友子さんがさっそく一文を。ありがとうございました。愛読・応援いただいているみなさんからもっともっと、ひとことずつメッセージをよろしく・・3月のスローライフ「さんか・さろん」は、映画と講演の夕べ 3月の「さろん」は、柔らかに経済を学ぶ。しかも豪華版です。さろんで初めての映画会。「幸せの経済学」。加えて学会学長の神野直彦教授が、映画を題材にとった“特別講義”をしていただけるというメニューなのです。 ドキュメンタリー映画「幸せの経済学」(ヘレナ・ノーバーグ=ホッジ監督)はヒマラヤ辺境の小さな村・ラダックが、押し寄せるグローバリズムの波に、伝統的な生活スタイルから文化や誇りまで奪われる。、監督はスェーデン出身の女性。人と人の絆を取り戻すローカリゼーションを提案する。3.11後の日本の行方に大きなヒントを与えてくれる映画です。 …3月21日(水)19時~20時30分(18時40分受付開始) ※通常のさろんは第3火曜日ですが、今月は20日祝日のため21日の開催。○場所…都道府県会館(千代田区平河町2-6-3)3階会議室○主催…スローライフ学会 ○参加費…1000円<会員外2000円、学生500円>○プログラム…神野直彦教授(スローライフ学会学長)講演と映画(68分)【申込み】NPO スローライフ・ジャパンへ。電話 03-5312-4141 FAX 03-5312-4554メールは下記項目にご記入の上、へお送りください。 当日申込みもOK。当日連絡は090-7433-1741野口まで ==============3月21日(水)「さんか・さろん」に参加します。●氏 名 :●連絡先電話番号 :●所属 :【スローライフ学会員以外の方は下記もご記入ください】●住所 : ●メールアドレス :●あなたを紹介した学会会員名:==============■私たちはいつもスローライフの動きを応援しています。鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/pr/koryu/index.html岩手県遠野市 http://www.city.tono.iwate.jp/鳥取市 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1196922905996/index.html佐賀県小城市 http://www.city.ogi.lg.jp/日本テレネット株式会社 http://www.nippon-tele.net/クオリティ株式会社 http://www.quality.co.jp/アース・デザイン・インターナショナル(edi)株式会社 http://www.edi.ne.jp/株式会社サンクス・ツー http://www.thanks2.jp/=======最後までお読みくださって、ありがとうございました。このメールマガジン、あるいは当団体へのご意見、ご質問はこちらへこのメールは毎週火曜日の発行です。NPOスローライフ・ジャパンとのご縁を頼りにお送りしています。初めて受信される方も含めて、お気軽にお付き合いください。今後、このメールマガジンの送信が不要という場合、あるいはメールアドレスの変更をご希望される場合もこちらへご連絡ください。この「週刊スローライフ瓦版」、バックナンバーをアップしています。まだご覧になっていない方、こちらからご覧ください。http://www.slowlife-japan.jp/modules/mailmagazine/details.php?blog_id=2=======Copyright(C) NPO法人スローライフ・ジャパン スローライフ学会〒160-0002東京都新宿区坂町21 リカビル301TEL 03-5312-4141 FAX 03-5312-4554 http://www.slowlife-japan.jp/”